
アメリカの動物園と寄付
静岡市立日本平動物園 佐渡友 陽一
筆者は、静岡市から姉妹都市への職員派遣研修により、アメリカ中央部のネブラスカ州オマハ市に約1年間滞在する機会を得、そのうち4ヵ月を同市のヘンリー・ドーリー動物園で教育部門の実習生として滞在した。
オマハは都市圏人口約50万だが、同園は年間120万人もの入園者数を誇る全米屈指の大規模園だ。ずいぶんと長い園名は、1952年にオマハ市の直営から協会として独立してほどなく、地元新聞社社長であったヘンリー・ドーリー氏の遺産が寄付された時についたものだ。
1. 動物園経営における寄付金
ヘンリー・ドーリー氏の事例を引き合いに出すまでもなくアメリカの動物園経営における寄付金の割合は、日本とは比較にならないほど大きい。いくつかの園館の収入を調べたところ、平均して30%が入園料(メンバーシップ収入含む)、31%が行政補助、そして寄付金が30%だった。残りの9%は売店や遊具などの利益が4%、基金運用益その他が5%というところだ。
 |
「リード・ジャングル」 1992年にオープンした世界最大の屋内ジャングル。建設費約15億円のうち半額がリード氏の遺産から寄付された。 |
ヘンリー・ドーリー動物園の場合、展示建設はすべてこの寄付金によって賄われている。展示には半額以上を寄付 した人の名前が冠せられ、たとえば「リ ード・ジャングル」という世界最大の屋内ジャングルの建設費は、リード財団からの寄付で半額が賄われた。また、「スコット水族館」の寄付者は地元ゼネコンの社長で、この水族館の建設に当たっては社長本人と会社から多額の寄付が寄せられた。この水族館の建設は当然のごとくこの会社が請け負っている。
かくして、市有地である公園の敷地に(土地は100年間の無償借り受け)、何十億円もを投資した巨大展示施設が、動物園協会によって建設されているのだ。 さて、このように多額の寄付をした人が動物園の最高意思決定機関である理事会のメンバーとなり、園長から課長の人事・予算決算などの決定権を持つ。それでは園長は何をするのかといえば、その最大の仕事は新しい展示などのプランを打ち出して、寄付金を集めることだ。ヘンリ―・ドーリー動物園の園長ドクター・シモンズは園長歴36年のベテランで、同園をかくも大きくしたのは、ひとえに彼の企画力と人脈によるものといえる。
2. 準公金としての寄付金
 |
デザート・ドーム(建設中) 世界最大の砂漠ドーム。ヘンリードーリー動物園の最新展示で、建設費約40億円のうち半額が1人の人間から寄付された。 |
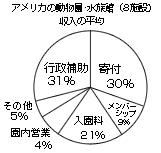 |
 |
ボランティアのリーダー達たち ドーセントの部屋に貼られたボランティアのリーダーたちの写真。璧富な人材としっかりとした組織を持つドーセントは、動物園の教育部門の中核となっている。 |
しかし、なぜアメリカ人はそんなに寄付をするのだろうか?実のところ、アメリカ社会における寄付金の意味合いは、日本で暮らしていると想像できないものがある。
まず、これは日本でもよく指摘されることだが、税金対策という意味がある。しかし、それ以上に大きいのは企業のイメージアップや、地域の名士としての立場の確保という宣伝効果だ。実際、私は2軒の中流家庭にホームステイしたが、「どこどこの施設に寄付をした、どこどこの社長の誰それさん」という認識はこく常識的なものだった。逆に、大会社の社長にもかかわらす目立った寄付がない人とは、「あの人はどこに寄付をするのだろう」と別の意味で注目を集めることになる。高額寄付者を動物園協会の理事とするのも、彼らに地位を提供するといった意昧合いが大きい。
日本で「誰それが大金を寄付をした」などといえば、「そんなに儲けるとは、あくどい商売をしているに違いない」と思われるのが落ちだが、アメリカでは寄付は肯定的どころか、当然の行為として受け入れられるのだ。
日米のこの違いは、富の分配システムの違いとして説明できる。つまり日本では公的資金のすべてを税金として集め、官僚がその配分を決めるが、アメリカでは自ら稼いだ金をどのように活用するかが選択できるといえる。結果、宗教団体はもとより、動物園や博物館等の文化施設、病院や諸々の研究機関が寄付金によって運営される社会が成立している。例えば、遺産で財団を作ると相続税が掛からないが、その基金運用益は地城の非宮利団体に還元するという制度がある。よく「遺産の寄付」といわれるが、そのほとんどは実はこのような財団によるものだ。そして、寄付者はどこに寄付するのが一番効果的か、すなわちどの団体のプランが一番市民に好感を持って受け入れられるかで寄付する対象を選ぶ。
かくして、動物園はひとかたならぬ努力で寄付者確保に乗り出す。高額寄付者を動物園協会の理事として経営陣に迎えたり、展示に高額寄付者の名前を冠するのがその最たるものだが、寄付者の名前を園内で掲示するのも広く行われており、企業やロータリークラブに園長や課長が出向いては、新展示フランのPRに余念がない。果ては、動物園で名士を集めたパーティーを実施し、地元画家の絵画や動物の里親の権利をオークションに掛けたりもする。 寄付金獲得のための部門を持つ園館も珍しくない。
3少額の寄付、時間の寄付
アメリカの動物園が必要とするのは、このような高額寄付ばかりではない。
少額の寄付の筆頭はメンバーシップだ。 これは、年間入園券であったり入園割引券であったりするが、寄付として所得税控除が認められている。なお、社員の福利厚生の一環としてメンバーシプ購入の全額ないし半額を補助する企業も少なくない。ヘンリー・ドーリー動物園では収入の17%をメンバーシップが占めており、入園料を上回る。
もう一つ重要なのが「時間の寄付」、すなわちボランティアだ。日本であれば先ずはひんしゅく物だが、アメリカではボランティア活動を、その活動時間分バイトを雇ったらいくら掛かるかを 金額に換算して評価するのが一般的だ。 ヘンリー・ドーリー動物園では、年間 15,000時間、額にして約1,200万円分のボランティア活動がある。
このように、アメリカの動物園は運営のいたるところを市民や企業からの寄付に頼っている。逆にいえばこれは 、入園料や売店収益などで平均40%足らずしか収入を得られない動物園の宿命でもある。日本では全収入の30%もの寄付を確保するのは難しいだろうが、であればこそどうあるべきか見据え、将来に向けて進んでゆくことが求められると感じている。
(さどとも よういち)