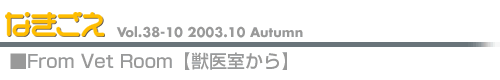
このところ立て続けに「新型肺炎SARS」や「サル痘」などの感染症が新聞やテレビで話題になりました。これらは人獣共通感染症または、その可能性があると考えられています。そこで、今回は人獣共通感染症についてごく簡単に触れてみたいと思います。 まず感染症ということばですが、病原体とよばれるものがヒトや動物の体に住み着いて起こす様々な病気のことをいいます。病原体となるものはウイルス、細菌、カビ、寄生虫など多くの種類があります。最近では、これらのよく知られた病原体のほかに、狂牛病(ウシ海綿状脳症:BSE)などの原因となるプリオンといわれる感染性のタンパク質なども知られるようになりました。 さて、世界保健機構(WHO)では人獣共通感染症とは人とそれ以外の脊椎動物の間で共通の病原体によって起こる感染症をいうとしています。人獣共通感染症の中には、食物由来の食中毒なども含まれます。また、狂犬病のような人や他の哺乳類に広く感染し、発病すればほとんど死んでしまうようなもの、他の動物ではほとんど無症状であるのに人にかかると時には命に関わるほど症状が重くなるもの、あるいは、人ではほとんど症状がないのに、逆に他の動物では症状が重いものなど様々です。これらの病気が注目されるようになってきた背景には新興あるいは再興感染症という病気が関係あります。1980年WHOは天然痘撲滅宣言を行いました。これは種痘などの普及に力を尽くした多くの人々のすばらしい成果でした。このとき多くの人々が天然痘以外の感染症も同様の努力でいずれなくなることになるだろうと思っていました。しかし、天然痘撲滅宣言より10年ほど前から、これまで知られていなかったエイズ(後天性免疫不全症候群)などの新しい感染症(新興感染症)やすでに存在が知られていた感染症(再興感染症)の発生があいついで起こり、まだまだ警戒しなければならないことが次第に明らかになってきました。また、これらの新興および再興感染症の多くが人獣共通感染症であることも分かってきました。新興あるいは再興感染症の発生は交通の発達によって地球規模で人や物が移動するようになったこと、これまで人が入っていかなかった場所にも開発等で入り込むようになったことが原因のひとつと考えられます。 ところでSARSの場合ですが、中国で食用にされているハクビシン、タヌキ、イタチアナグマでSARSウイルスに遺伝子構造の似たコロナウイルスが検出されたと中国の研究機関が報告しました。ただし、ハクビシンで検出されたウイルスの量や人に感染するかどうかも確認されておらず感染源のひとつとしての疑いに過ぎません。ところが、この報道のためか、わが国でも動物園のハクビシンは大丈夫かという問合せを受けた動物園もあったようです。ちなみに天王寺動物園でもハクビシン1頭を飼育していますが、20年も前から飼育している個体で、この間担当者などがSARSに感染したという事実はありません。また、日本ではタヌキとハクビシンは生息していますが、過去に日本でこれらの動物と接触してSARSに感染したという事実もありません。日本産のハクビシンやタヌキではSARSウイルスに感染する機会はなかったのではないかと予想されます。また、日本の動物園が大陸からハクビシンを導入したのは30年以上前で、その際、SARSウイルスが持込まれたという可能性はないのではと考えます。さらに現在ではSARSの発生した中国からのハクビシンは事実上輸入できなくなっています。 また、動物園では園外からの入園動物は一定期間の検疫を行って病気の有無を確認してからお客様にお目見えすることになっています。そのため、動物園のハクビシンやタヌキはSARSについても大丈夫といえるのです。むしろ、病気などの情報の少ない野生動物をペットとして一般家庭で飼うことのほうが問題が大きいと考えられるでしょう。 飼育課 高橋 雅之
|
||
