
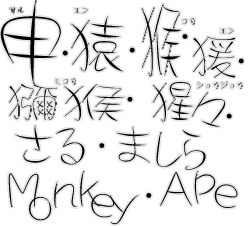
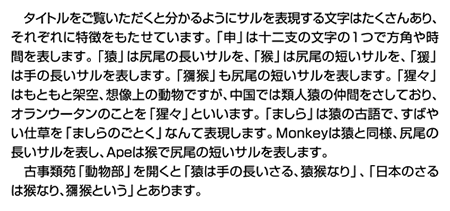
 |
|
原猿の仲間に入れる
学者もある「ツパイ」 |
現在、地球上に生息する霊長類(サルの仲間)は10科58属175種余りと言われています。(ヒトと食虫性の高いツパイなどは除く)
分布は赤道の熱帯から高度2500mの高地、或いは分布の北限と言われる日本の下北半島までの広い範囲に及びます。
サルは知能が高く、賢く、人の生活圏の身近にいることから、洋の東西を問わず昔から擬人化して人に例えられたり、また、人から揶揄されたりして伝説やおとぎ話の主人公に取り上げられてきました。霊長類学の研究が進んだ現在、ヒトとチンパンジーは進化の上で最も近いところで分岐し、遺伝子距離も短いと言われ、学者の一部ではチンパンジーの人格を尊重し「チンパン人」と称するほどです。ヒトとサルの違いを隔てるのにヒトは二足で歩行し、家族を形成し、言語、文化を持ち、生産、備蓄、分配の能力を持ち、火を起こし、道具を作り、道具を使い、分業と協調ができる動物と定義しています。しかし、現在では類人猿の能力開発によって、言語の発声という機能はないもののヒトとの間で会話が出来るチンパンジー「アイちゃん」が現れたり、会話のほかにマッチを擦り、火を起こす術を知っているボノボ「カンジ君」が現れたりと霊長類学界では新発見や新しい能力の開発に沸き立っています。
さて、平安時代に興った軽妙な芸能に「猿楽」があります。これは滑稽な動作、振舞い、物まね、言葉芸などの芸能を言いますが、鎌倉時代に入って演劇化して能、狂言の元となりました。歌舞伎の一座に猿若座がありましたが、これは歌舞伎の道化ものを得意としたことから名付けられたものです。また、猿若とは歌舞伎の道化役のことを言います。
狂言の演目の1つに「靭猿・うつぼざる」があります。「靭」とは武士が背負う矢束を入れる容器ですが、高級な武士では巻き狩りなどをする際に、装束を競うのに矢を入れる靭に羽飾りや、獣のなめし革を掛けて誇示したといいます。
「靭猿」では大名が猿曳きと出会いますが、その際に大名が猿の毛並みにほれ込んで、猿の毛皮を靭に掛けたいと所望しますが、断られます。貸す、貸さないのやり取りの間に大名が痺れを切らして猿を矢で射とうします。これには猿曳きも負けて矢を射掛けては皮が台無しになるので、猿曳きが棒で猿を失神させるといい、その場で猿に大名の道理の通らない話を懇々と言い聞かせ因果を含みます。いよいよ猿曳きが棒を打ち下ろそうとした時に、猿はとっさにその棒を取って日頃教えられている舟こぎの真似をしたことから、そのけなげな姿を見て大名が涙し、感激して、身につけているものを次から次へと恩賞として与え、一緒に踊るという狂言です。
 |
|
「厨馬図」室町時代に見る厨扱いのサル(本圀寺蔵)
|
中国にも猿を題材に取った有名な演劇があります。京劇の「西遊記」孫悟空ですが、これも見せ場は猿の軽妙な動作、仕草、激しい動きが注目されるところです。
このように猿を題材にした演劇や芸能はアジア、アフリカなどの地域で広く見られます。
猿、そのものを使った芸能に猿回しがあります。戦後、一時廃れてしまったのを山口県光市の村崎義正氏によって大成、復活し、一時はテレビでも良く取り上げられ「周防猿回しの会」として有名でした。また、良く似たものに「日光さる軍団」なるものもテレビで見うけられました。私自身も昔、若い頃に天王寺公園で猿回しを見たのを覚えています。
さて、元々猿回しと言われる猿曳き(猿引き)はその昔、貴族、武士の馬の無病息災を願う厩の悪魔払いの「厩祓い・厩舎祭」として馬や厩の守護神である猿が御幣を持って祓い清めたことが始まりで、滑稽な猿回しの芸はお祓いの余興として演じられていたものでした。猿曳きは平安時代から鎌倉、安土桃山時代と自由に往来を行き来できる職業でしたが、江戸時代に入って身分と縄張りが固定され、猿曳きの業が世襲されるようになり、転業も自由に出来なくなりました。江戸では15軒の猿曳きに免許が交付され、正月、5月、9月には江戸城に登城して、将軍の前でお祓いだけでなく猿舞までも披露できる機会が与えられました。扶持は旗本よりも高く厚遇されていました。また、京の朝廷には紀州の猿曳きが参内したとあります。(このあたりの様子は室町時代の「厩馬図」(京都・本圀寺蔵)にうかがえるようです。)この時代、武士社会や公家達では良い馬を持つことがステータスで財産でもありましたので、大名達もこぞって「厩祓い・厩舎祭」を行い猿曳きを優遇しました。しかし、明治維新後、幕藩体制が解体し、武士の庇護を受けなくなると猿曳きの身分と生活は苦しくなり、猿回しの芸は衰退しました。
猿回しの芸能は日本のほか、インド、中国ではアカゲザルを使ったもの、南米ではオマキザルを使ったもの、ヨーロッパではバーバリエイプを使ったもの、古代ではヒヒを使ったものなどの報告があります。
 |
|
南タイでココヤシの実を
採るように訓練される 「ブタオザル(オス)」 |
このほか、サルを使役に使ったり、使役の様子をショーとして見せるのに「ブタオザルのヤシの実採り」があります。これは南タイで80年以上前から行われているもので、南タイのスラータニには「ブタオザルのココヤシの実採取訓練センター」があって、ブタオザルを使役やショーに使うため、授業料(30000バース・日本円で1万円)を取って6か月から8か月間預かって訓練をしています。訓練のはじめの頃は地上で箱の中に軸を通したヤシの実を手と足を使って回転させるという動作を教えられます。その次には実についた柄を回転によってねじ切る動作を教えられます。その次には木に攀じ登ってという具合に、徐々に難度を加えていって調教を完成させます。良く調教された成績の良いブタオザルは1日にココヤシの実を800から1000個をもぎ取るそうで、やはりオスのほうが体格も大きく成績も良いようです。
ココヤシの実は中果皮の繊維や胚乳のコプラ、果汁とも余すところなく使えるため重宝し、重要な収入源となっています。通常、ココヤシの実の採取は人の手で長い棒の先に鎌を取り付け、切り落としたり、木に攀じ登って実を落としたりしていますが、非常に危険が伴うのと効率が悪いので、一部の地区ではブタオザルを使っています。しかし、なぜか使う猿はブタオザルのみでほかの種類のサルを使ったヤシの実採りは見かけません。ブタオザルのヤシの実採取は南タイのほか、ブタオザルの分布地域であるスマトラやマレーシアの一部でも行われています。
また、マレーシアの森林局ではブタオザルのこの能力に着目し、植生調査のために植物標本を採らせています。
このようにサルや動物を使った祈祷、厄払い、狩猟、漁労の話は民俗学や民族動物学の書籍に詳しく、読んでみると結構楽しいものです。
天王寺動物園長 中川哲男
1.猿回し上下ゆ:1983年12月 村崎義正 筑摩書房
2.民族動物学、−アジアのフィールドノートから−:1995年9月 周達生 東京大学出版会
3.古事類苑・動物部:1985年5月 神宮司廳 吉川弘文館
4.サル学なんでも小事典:1992年5月 京都大学霊長類研究所
5.干支の動物誌:1994年10月 阿部 禎 技報堂出版