
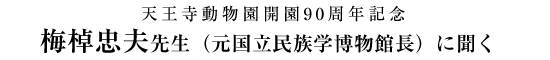
 |
|
梅棹先生と鼎談中の若生教授
|
◆はじめに
昨年、天王寺動物園が開園90周年を迎えた際、かねてからお会いしてお話を伺いたいと切望しておりました、国立民族学博物館の初代館長で現顧問の梅棹忠夫先生を2005年8月31日、お訪ねする機会に恵まれました。若生謙二大阪芸術大学教授と民博の一室で梅棹先生を囲んで約2時間にもおよぶお話をさせていただき、動物園談義とともに天王寺動物園へのお祝いメッセージもいただくことができました。梅棹先生が今から40数年前に天王寺動物園の園長に招聘されたものの固辞された理由などを誌面でご紹介しましょう。
■若生 「私は大阪芸術大学の環境デザイン学科で造園学をおしえております。今から15年ほど前になるのですが、こちらの宮下園長(註:当時飼育課主査)のご依頼で天王寺動物園の将来計画を作成することになり、それにたずさわってまいりました。その頃ですが、先生が天王寺動物園の園長に招聘されたというお話を『日本三都論―東京・大阪・京都』(1987年 角川書店)の中でよみ、大変おどろきました。」
■梅棹 「そんなこともありましたね」
■宮下 「私は獣医師として天王寺動物園にはいりまして32年になるのですが、はからずも天王寺動物園の開園90周年にあたる昨年4月から15代目の園長に就任させていただきました」
■梅棹 「ほう、15代目ですか」
■宮下 「先生が天王寺動物園の園長にならないかとすすめられたがことわったという記述を拝見し、もし先生がその当時、園長をおひきうけになっておられたら天王寺動物園はどのようにかわったか、あるいは日本の動物園全体がどうなっていただろうかと想像するだけでもわくわくします。先生が園長をおことわりになった理由をぜひうかがいたいと長年おもっておりました」
■梅棹 「大阪市の水道局におられた近藤正義さんってご存じですか?私は京都大学動物学の出身で、近藤さんもおなじ動物学教室の先輩でした。私は当時、大阪市立大学で助教授をしていたのですが、近藤さんがある時に天王寺動物園の園長をしないかという話をもってこられた。だいぶかんがえたけど、おことわりするしかないな・・と。それには前例があって京都大学動物学教室のだいぶ先輩ですが、川村多實二教授という方がしばらく京都岡崎の動物園長を兼任しておられた。近藤さんから動物園長の話があったんで、宮地伝三郎先生(註:京都大学理学部教授)に相談にいったんです。おもしろい話やなとおもったけど、どうかんがえても私には務まらない。動物園長なら毎日出勤しないといけないでしょう?当時は助教授というのはのんきな職業でね。大学へ出ていってもいかなくてもいいんですよ。私は京都の北白川にすんでいて、そこから大阪市立大学にかようのですが、とおいですからね。だからしばしば行かなかった。そんな具合だから動物園長はとてもだめだと近藤さんにはおことわりしたんです。近藤さんは、惜しいなって残念がっておられた」
■若生 「宮地先生のほうからは川村先生がおやめになられたことで、梅棹先生にもやめられたほうがいいとお話でもされたんでしょうか」
■梅棹 「川村先生は京大教授を務めながらの兼任で、どの程度、実際に京都の動物園に関与されていたかは知りません。兼任でも園長は園長ですから何度か行っておられたでしょうけどね」
■若生 「実際には川村先生が園長をなさった期間は1年2ヵ月のようです。動物園界では上野動物園で東京帝国大学の動物学の教授をされていた石川千代松先生が実質上の園長を7年間されていますが途中で退職されています。日本で最初の上野動物園と次にできた京都の動物園が両方とも帝国大学の教授を園長にむかえたにもかかわらずうまくいかなかった。動物学と動物園は密接なつながりがあると思いますが、わが国では動物学と動物園がはなれていくというか・・・」
■梅棹 「そうですね。動物学教室にいるときも動物園とは全然関係がなかった。現実には私のまわりで動物園に関係した人は一人もいなかった。だから、近藤さんからその話があったとき、宮地先生に相談したら私が動物園をやることについてあまり積極的じゃなかったですね。伝統的に動物園というのは獣医さんの仕事で、動物学の人間がやれるわけがない、そういうかんがえがあったんです。それはたしかにそうやった。ベテランの獣医さんがやるべき仕事で、動物学の連中はまったくある意味で理論ばっかりですからね、現実に動物あつかうことはぜんぜんできない。うちで飼っていた猫が病気になったが、わたしにはなすすべがなかった。動物学者が猫の病気も治せなくてどうすると家内がいうんですが、わからんものはわからん。無理な話です。動物学をやってたといっても、私らは非常にちいさい動物をあつかうことがおおいんです。おおきな哺乳類は、ほんまに知らん。顕微鏡でみるようなのばかりみてますから。無理です」
■宮下 「今、先生のお話の中で動物園の園長は獣医師が一番いいとおっしゃっている中で、私は自身が園長になっておもうんですが、日本には92の動物園があるんですが、そのうち獣医師が園長をしているのは約30、三分の一ほどあります。それ以外といいますと、ほとんどが事務職の人で2年ぐらいの任期でかわっていかれる。ぜんぜん動物のことをごぞんじない方が園長でこられるか、ずっと動物園で仕事をしていた獣医師が園長に昇任するか、そのどちらかがほとんどです。ところが欧米をみますと、結構、動物学に精通され博士号をもった方が園長になっておられて、反対に獣医師や事務職の方が園長になっているのは非常にすくないですね」
■梅棹 「そうですか、不思議やな」
■宮下 「不思議なんです。日本で動物学をおさめられた方がなぜ園長をしないのかというのが長年の疑問でした」
梅棹「ほとんど例がないな」
■宮下 「先ほどの石川先生や川村先生にしても本当にみじかい期間しかされなかったのは、動物学と動物園がやはりなかなか融合しなかったからでしょうか」
■梅棹 「融合しないなあ。ところで私は京都市役所の佐々木時雄さん(註:京都市動物園長1962年4月〜1968年9月)という人と非常に仲がよかった。ある日、おうたら、「えらいこっちゃ、わしは動物園にいかされた。動物のドの字もしらんのに」と。ほんまに私もびっくりしました。彼は動物とはおよそ関係のない人で、まったくの事務職です」
■若生 「すばらしい本をかかれましたね。佐々木時雄先生は」
■梅棹 「あの本(註:『動物園の歴史』1975年出版、西田書店)は、じつにいいんですよ」
■宮下 「ちょうど30年ほど前に出版されましたが、動物園のバイブルという感じですね。私も何回も熟読しましたが、あれをよめば動物園の歴史が本当によくわかります。日本と世界と二つにわけてかかれてました。」
■梅棹「そうです。彼は、それまではほんまの素人やったけど、動物園長になってから勉強したんですね。物しりです。あの本は名著ですね」
■梅棹 「私は小学校時代に、ずいぶんと京都岡崎の動物園へかよっているんですよ。当時、岡崎の動物園へいくと、天然色の絵のかいた動物のカードを、20枚1箱くらいを箱にいれてうっていて、いくたびに一箱ずつかって、それをたくさんもっていました。自分でも絵をかいて、マニアですね、すきでやっていた。後に、長じるにおよんで動物学をやるようになって本職になってしまった。動物園についての少年時代の知識がだいぶ役にたっています。
■梅棹 「先生が少年時代に京都の動物園にかよって、そういうものを買ったり実際の動物をみられたことが後に先生が動物学の世界にはいっていかれる動機づけになったのですね」
■梅棹 「たしかにそうです。そのとおりです。私は登山家ですから山をあるきます。それと動物という趣味が合流したのです。私は子どものときから昆虫をあつめてて、昆虫標本を自分でこしらえて、昆虫のコレクションをずいぶんもっていました。とにかく、大学では動物学をやると決めていたのですよ。山へいってますから、興味の中心は自然、生態学なんです。自然生態学をやって世界各地のいろんな環境をみて知っています。アジアも、かなりよく知っています」
 |
|
梅棹先生と緊張気味の宮下園長の記念写真
|
◆あとがき
2時間があっという間の鼎談でした。梅棹先生の関心が昆虫コレクションから動物学へ、さらに生態学から民族学へと変わっていかれるなかで、40数年前に天王寺動物園とほんの一瞬の接点があったことを知っている方は少ないでしょう。その時に梅棹先生が園長をお引き受けになっておられたら、日本の動物園界は激変していたことでしょう。いや、世界の動物園界も大きく変動したかもしれません。惜しい機会を取り逃がしたものと本当に残念至極です。しかし、私たちはZOO21計画を実現する過程で、梅棹先生の展示学や世界観を学び、それを実現しようと努力してきました。その意味では、天王寺動物園の生態的展示は、梅棹先生の思想を継承しているものと自負しています。
(文責:宮下 実)
|
梅棹忠夫先生プロフィール 1943年 9月 京都帝国大学理学部卒業 |