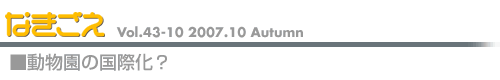
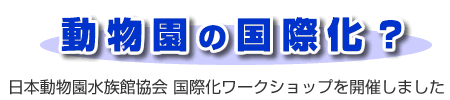
| 日本には、たくさんの動物園や水族館があります。ご<小規模なところを除いても、その数は160を超えています。そのほとんどが、社団法人日本動物園水族館協会(以下、日動水)の会員となっています。もちろん天王寺動物園もその一つです。 今年の5月、日動水の総会が大阪で開催されました。年に一度の総会には各施設の園館長が集まり、話し合いが行われます。今年のテーマは国際化でした。動物園水族館も世界的な視野で活動する必要性が高くなっています。動物は野外から捕獲しさえすればいいという時代ではありません。調査研究を進めながら計画的に増やすことを考えなければならない時代です。野生動物の保護増殖を進めるためには、国際的な協調は不可欠なのです。 海外との情報交換を行い、日本の動物園水族館の国際戦略について議論を深めるために、今回の総会には世界動物園水族館協会(WAZA)、保全繁殖専門家集団(CBSG)、国際種情報システム機構(ISIS)の代表者をお招きしました。 WAZAは、日動水を含む世界各地の動物園水族館協会や主要な施設による組織で、動物園水族館の世界的な方向性を決めるにあたって強い影響力を持っています。 CBSGは野外の希少動物の保全を進めている国際組織で、動物園水族館が希少動物保全に関わるにあたって重要な役割を果たしています。ISISは世界70カ国以上の動物園水族館を会員に持つ組織で、飼育動物に関する様々な情報をデータベース化し共有することで、情報の有効利用に貢献しています。 これらの国際的な組織の代表が集う貴重な機会を利用し、より多くの方が共に考えられる機会を設けるために、総会の前後に大阪と東京でワークショップを開催しました。今回は大阪でのワークショップの様子をご紹介します。
大阪ワークショップは、5月21日と22日に、天王寺公園にある映像館で行われました。参加者の事前募集を行ったところ、動物園水族館関係者に限らず、大学関係者や専門学校生など様々な方々に参加していただくことができました。
2つ目のセッションでは、ISISの新しい飼育動物管理システムについての説明が行われました。 ZIMSと呼ばれるこのデータベースシステムは、世界中の動物園水族館が、それぞれの施設で飼育している動物の情報を共有するためのものです。このシステムによって、どんなことが可能になるのでしょう?
3つ目のセッションは、カエルツボカビ症という感染症に間するもので、CBSGにより進められました。両生類の絶滅が世界的に加速していますが、その主な原因の一つが力工ルツボカビ症だと考えられています。中南米やオーストラリアなどでは、短期間のうちに多くの場所でカエルツボカビ症によリカエルが絶滅してしまいました。この感染症は、これまでアジアでは確認されていませんでしたが、残念ながら昨年末に日本国内のカエルから検出されてしまいました。今回のセッションでは、CBSG議長のロバート・レーシー氏ならびにCBSG両生類プログラム担当者のケビン・ジッペル氏からカエルツボカビ症の病原性、発生状況、予防や対策、国際的な対応といった点について解説を受け、日本での対策などについて検討を行いました。日本のカエルに及びつつある脅威について理解し、積極的な対策が必要であることを実感することができました。
3つのセッションは、別々のコーディネーターによって、全く視点の異なったテーマに沿って進められました。しかし、その根源は共通で、いずれも今後の動物園水族館の進むべき方向を示す内容でした。国際化とは、地域を越えて同じ目標に向かう過程で自ずと達成されることであり、目標達成の手段に過ぎないということを、このワークショップが示してくれたと思います。 (高見 一利) |



