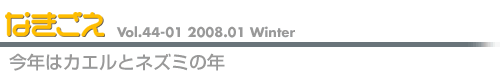

|
今年はカエル年、などと書き出すと干支のネズミがいつの間にカエルにと皆さん驚かれるかもしれませんね。世界的な自然保護団体や野生動物の保護に取り組んでいる大きな組織が、2008年をThe Year of the Frog 「カエルの年」と名づけ、全世界で一大キャンペーンを展開し始めました。昨年8月にハンガリーのブダペストで世界中の動物園の園長が集まる世界動物園水族館協会総会が開かれ、私も参加してきましたが、この会議でも2008年をカエルの保護、その生息環境の保全、カエルの恐ろしい感染症であるツボカビ症対策などに取り組むという決議が出され、今年は「カエルの年」としてその保護事業を展開することになりました。天王寺動物園ではいち早く昨年5月にツボカビ症のシンポジウムを開催し、さらに11月にも大阪市立自然史博物館と共催でツボカビ症対策のシンポジウムを開催したところです。
日本では新年は干支のネズミの話題で盛り上がっていますが、今や野生動物の世界では絶滅の危機に瀕(ひん)する動物の保護、その生息地の保全などが大きな課題として取り上げられ、特にツボカビ症の脅威にさらされているカエルについては、全世界の人々に関心と理解を持っていただこうとしているのです。新聞やテレビ、インターネット等でご存知の方も多いと思いますが、世界各地で多くのカエル類がこのツボカビ症によって急激な個体数の減少や地域によっては絶滅の危機に陥っています。そのツボカビ症は一昨年の12月に日本国内のカエルにもとうとう感染の確認がされました。カエル類の絶滅や激減がもし起これば、カエルを餌として食べている動物にも影響を与えますし、カエルが食べる昆虫、特に農業害虫などが急増することで日本の生態系そのものにも大きな影響が出ることでしょう。今年1年、カエルのツボカビ症にご注目ください。
当時の飼育担当者が野ネズミの生態系で果たす役割や家ネズミが世界中に広がったのは人間が原因であることなど、分かりやすい解説を掲示し、このドブネズミ展示は新聞などにも紹介されて結構話題になりました。
しかしどうもネズミのイメージというのは良くありません。これは人間社会で身近に暮らす家ネズミが食べ物をくすねる、木製品を齧(かじ)る、電気コードや通信ケーブルを切断する、家の中を排泄物で汚す、そしてペストで代表されるように病原性の高い細菌やウィルスを媒介するなど、人間の不利益になることに大きく関与しているからでしょう。そのため生態系の中で重要な役割を果たしている野ネズミまでが同罪に問われているのはかわいそうな気がします。
ネズミというのは分類学的に齧歯目(げっしもく)(ネズミ目)というグループに属します。この中にはおなじみの動物であるハムスターやリス、プレリードッグ、ビーバー、ヤマアラシ、外来動物の野生化で問題になっているヌートリア写真⑤などが含まれています。この地球上に現存する哺乳類は約4100種、その内、齧歯目の動物はなんと1700種類、40%を超える大グループを構成しています。しかもその分布する地域は、南極大陸を除くすべての大陸と、ほとんどすべての島々。つまりこの地球上で圧倒的に多くの種類を誇り、いたる所で生活をしているという、哺乳類のなかでも大いに繁栄しているのがこの齧歯目なのです。 (天王寺動物園長 宮下 実) |




