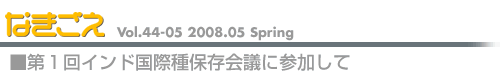
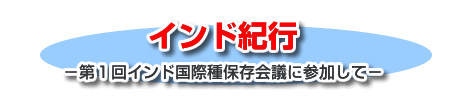
|
2008年2月21日から24日にかけてインド・デリー市で第1回インド国際種保存会議が開催されました。この会議は、インド国内の動物園における種保存事業を国際レベルに押し上げるために初めて開催されたものです。開催にあたり、インド政府中央動物園管理局から(社)日本動物園水族館協会に専門家の派遣の依頼がありました。そこで、同協会・種保存委員会の推薦を受け私を含む2名が参加しました。私はインドに生息するシシオザルの日本国内の血統登録(動物の戸籍管理)を担当しているため選ばれました。
ナマケグマ保護施設と同じアーグラ市近郊にあるタージ・マハルも訪ねました。さすが世界遺産!荘厳な雰囲気で歴史を感じました。
続いて訪れたインド国立動物公園は、1959年に開園した、インドで最も歴史ある動物園です。86ヘクタールという広大な土地に、インド原産の動物を中心に約2,000種22,000点が飼育展示されていました。シシオザルも展示されていましたが、インド南西部に生息する希少なサルにもかかわらず、広い放飼場に2頭しか展示されていなかったので、寂しく感じました。
さて、全体会議には、インド国内から約80名、海外から約30名の動物園関係者や研究者の参加があり、インドにおける動物園動物と野生動物の保全繁殖やその将来展望、動物園で飼育している動物の情報管理の必要性について議論されました。その後開催された分科会では、インドの動物園で飼育されている各動物種について論議を深め、最終全体会議で血統登録優先種や国際協力などインドとしての今後の保全繁殖の方針が決議されました。私が参加した霊長(サル)類分科会では、最優先種にシシオザルが選ばれ、インド国内の血統登録簿の作成はもちろんのこと、今後、早急に国内会議を開き、海外と連携した繁殖計画を策定することなどが決まりました。
もともとあまり英会話の得意でない私ですが、インドなまりのある英語に苦戦しながらも、日本の代表としてインドの種保存事業に参画できたことに誇りを感じました。 (竹田正人) |
||||||||



