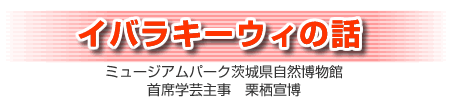|
キーウィの故郷といえば南半球の島国ニュージーランドであることは,皆さんよくご存じのことと思います。そのニュージーランドに,なんと「イバラキ」という名の野生のキーウィ(英名:ノース・ブラウン・キーウィ)がいるのです。イバラキとはもちろん茨城のことで,わたしたちは,「イバラキーウィ」と呼んでいます。
なぜ,イバラキーウィ?
わたしたち,茨城県自然博物館では,平成19年の夏「キア・オラ!ニュージーランド−キーウィと人がくらす島」展を開催しました。この企画展は,ニュージーランドの個性豊かな自然や外来種対策など自然保護への取り組みを紹介するもので,
天王寺動物園からもキーウィの剥製,骨格,たまごの標本をお借りし,飛べない鳥キーウィの体のつくりについても展示させていただきました。
|
|
|
イバラキーウィとレンジャーのペテさん(2006.12)
|
その半年前,平成18年12月,展示に向けてキーウィの保護活動の実際を取材するため,北島の大都市オークランドから車で北へ2時間半,ファンガレイキーウィ保護区を訪れました。対応してくれたのはキーウィレンジャーのペテ・グラハムさんでした。彼は野生のキーウィを定期的に捕獲し,その成長を記録する仕事をしています。その調査に同行させてもらいましたが,その際,捕獲したキーウィにはまだ名前がついていませんでした。そこで同行したわたしたちにちなみ,彼がそのキーウィに「イバラキ」という名をつけてくれたのです。
野生のキーウィをつかまえる方法
イバラキーウィとの出会いをもう少しくわしくご説明しましょう。ペテさんとの事前打ち合わせで,昼間でも野生のキーウィに会えると聞いたとき,私は,夜行性のキーウィにどうやって会えるのか,また,近づいたらすぐ逃げてしまうのではないかと疑問でいっぱいでした。しかし,調査に同行し,その疑問がとけました。キーウィには電波発信機が取り付けられており,キーウィが昼間ひそんでいるねぐらの場所がわかるのです。
さらに,驚いたことに,わたしたちが近づいてもキーウィは決して逃げ出したりしないのです。ペテさんは,大きなシダの葉がつもった茂みを利用したねぐらの中をライトで照らしながらのぞきこみ,キーウィの位置を確かめます。そして,さっと手を入れ,キーウィの足をしっかりと握って確保。あっさりとキーウィは捕まってしまいました。
なぜ,キーウィは走って逃げたりしないのでしょうか?
もともとニュージーランドには,イヌやネコ,イタチなどキーウィの天敵となるほ乳類は1匹もいませんでした。ヒトも住んでおらず,昔からの自然がそのまま残されたまさに鳥の楽園でした。そのため,キーウィ以外にも,カカポやタカヘなど飛ぶことをやめたニュージーランド固有の鳥が進化したのです。しかし,キーウィにとっても怖い存在はいました。ワシやフクロウの仲間です。そんな敵から襲われたとき,逃げ出したりせず,じっと茂みの中に身を隠している。それが一番安全な方法だったのでしょう。
しかし,約千年前,ヒトとともに様々なほ乳類がニュージーランドにやってきました。そうなるとこのじっとしているという習性が,外来種であるイヌなどに簡単に襲われてしまうことにつながり,その数が大きく減る原因の一つになってしまいました。
キーウィを守る取り組み
ニュージーランドでは,DOC(環境保全局)が中心となって危機的状況である野鳥の保護活動に取り組んでいます。キーウィについては,国内に5つの保護区を設け,キーウィの実態調査や天敵となる外来種の数のコントロール,卵の人工ふ化と成長後に自然に放すという取り組みを進めています。ファンガレイキーウィ保護区はその中の一つです。そこは牧場の中に島状に広がった6つの森からなり,その総面積は2,000haになります。イバラキーウィのすむラレワレワ地区では,51羽のキーウィに小型の電波発信機が取り付けられ,定期的に捕獲し,その成長が記録されています。
イバラキーウィのその後
今年の3月,再び,ファンガレイキーウィ保護区を訪問する機会がありました。今回は,「ニュージーランド子ども大使派遣事業」として,財団法人カメイ社会教育振興財団(仙台市)の助成とニュージーランド大使館,ニュージーランド航空の協力を受け,当館のジュニア学芸員4名にニュージーランドの自然保護の実際を体験してもらうため訪問したものです。
私は,イバラキーウィとの再会をとても楽しみにしていましたが,同時にとても不安でした。なぜなら,私が初めてイバラキーウィと会った時,その体重は約500gでした。キーウィのヒナのほとんどが,1kgになるまでにイタチやネコなどに襲われるなどして命を落としてしまうからです。
今回も,ペテさんの調査に同行させてもらいました。そして,念願のイバラキーウィとの再会を果たすことができました。体重は1.6kg。1年3カ月で,3倍にもなっていました。この大きさになれば,イタチなどに対して身を守ることができるようになるそうで,一安心するとともに,外来種の数をコントロールするという地道な努力の成果があがっていると感じました。とはいえ,より大型のイヌの脅威は今後も続きます。
ニュージーランドでは,国をあげて外来種問題に取り組み,着実に成果をあげてきています。「イバラキ」という名の野生のキーウィが,今,この瞬間も,ニュージーランドで元気に生きている。このことをたくさんの人に紹介し,ニュージーランドの外来種問題やその取り組み,さらには身近な外来種問題にも関心をもってもらう。そんな博物館活動を,イバラキーウィがこれからもずっと元気でいてくれることを願いながら進めていきたいと考えています。
(くりす のぶひろ)
|