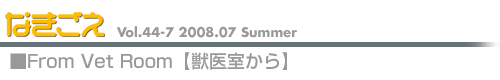|
|
検疫中のカエルたち
|
カエルツボカビ症という病気があります。昨年、テレビや新聞などで何度も取り上げられたので、ご存知の方も多いでしょう。カエルやイモリといった両生類だけがかかります。海外では両生類の絶滅を引き起こしているような恐ろしい病気です。カエルツボカビの感染力はとても強いと言われており、動物園に持ち込まれると飼育している両生類にうつって大変なことになる可能性があります。そこで、天王寺動物園では、この病気が日本で確認されてからは、両生類の導入を中止していました。
しかし、いつまでも両生類を取り扱わないというわけにはいきません。病気は怖いけど、両生類は飼育したい・・・。そこで、両生類に対する検疫を厳しくすることにしました。動物園では、新しく入って来るすべての動物について、病気を持っていないか検査します。多くの場合、検査の結果が出るまでに2カ月かかります。その間、他の動物と離して飼育します。その動物が病気を持っていたら、他の動物にうつしてしまうかもしれないからです。このように、検査しながら一定の期間隔離して飼育することを検疫といいます。
これまで天王寺動物園では、両生類の検疫をアイファー(爬虫類生態館)の中で行っていました。元から飼育している両生類とは別の水槽に入れることにしていましたが、同じ部屋の中に置くことがありました。しかし、カエルツボカビは感染力が強いので、同じ部屋の中で飼育していると、水しぶきが飛んだり、飼育員の手に付いたりして簡単にうつってしまう可能性があります。そのため、全く別のところで両生類を飼育するための場所を見つける必要がありました。
なかなか良いところが見つからなかったのですが・・・とうとう見つけました。昔休憩室として使われていたプレハブです。今はほとんど使われておらず、中には荷物がたくさん積み上げられていました。このプレハブから机や椅子、荷物をすべて運び出して、きれいに掃除しました。そして中をビニールシートで区切り、いくつかの小部屋を作りました。天井にもビニールシートを張り、それぞれの部屋が完全に別の空間となるようにしました。中にはお風呂のように大きなタンクを取り付けて、消毒薬を満たしました。こうして、数週間かけて手作りの両生類用検疫室が完成しました。
この検疫室の入口には鍵が取り付けられています。中に入るのは、限られた獣医師だけということに決めています。また、この検疫室の中で動物に触れる作業をした人は、その後の時間はアイファーに近づかないことにしています。動物が病気を持っていた場合、その病気を外に持ち出してしまい、さらにアイファーで飼育している両生類にうつしてしまうのを防ぐためです。
入口から中にはいると、一つめの小部屋です。ここでスリッパに履き替え、手袋をはめて白衣を着ます。次の小部屋には水道と流し台、消毒液のタンクがあります。飼育に使った水や水槽には、カエルツボカビなどの病原体がいるかも知れません。ここでは、そういったものを消毒し、病原体を無くしてから洗います。さらに奥に進むと、ようやく両生類の飼育部屋です。今は、たくさんの小さな水槽に分かれてカエルとオタマジャクシが飼育されており、検査結果が出るのを待っています。これらの動物の検疫にも、およそ2カ月かかることになりそうです。検疫室から出ていくときには、入ったとき同じルートを逆向きにたどります。飼育部屋から水道のある部屋に出たところで、使用した道具や手袋などをすべてタンクに張った消毒薬の中に沈めます。さらに次の部屋に出たところで、白衣とスリッパを脱いで、手を消毒します。そうしてようやく検疫室の外に出てくることができます。
目に見えない病原菌の取り扱いには気をつかいます。知らないうちに、私たちが動物の病気を広げる手助けをしてしまうことがあるからです。毎日の作業は少し面倒なのですが、きっちりと手順を守ることで病気の広がりを防げるのなら、たいした手間ではありません。
(高見 一利)
|