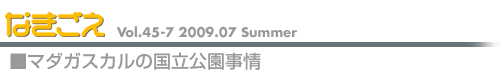

|
マダガスカルは、世界で4番目に大きな島。グリーンランド島、ニューギニア島、カリマンタン(ボルネオ)島に次ぐ広さで、面積は59万平方キロメートル、日本の国土面積の約1.6倍にあたります。かつては、アフリカ大陸やインド亜大陸などとともにゴンドワナ大陸を形成していましたが、中生代に他の大陸から分かれて孤立し、他の場所でみられない固有の動植物が栄えるようになりました。なかでもキツネザル類(原猿類、レムール類)の豊富さは他に類がなく、その種数は70種以上にのぼるともいわれます。
動物好きの皆さんには、ぜひともこのキツネザル類について紹介したいのですが、残念なことにわたしは動物学者でなく、手持ちの写真も多くありません。わたしは、古い住人であるキツネザル類でなく、新参者であるヒトの生活について研究を続けてきました。キツネザルの話題は別の機会に譲ることにして、今回はヒトと動物たちの接点ということで、マダガスカルの国立公園や保護区の実態について御紹介したいと思います。 じつは、マダガスカルは、公園行政の関係者からは画期的な国として知られています。きっかけは、2003年9月に南アフリカのダーバンで開かれた世界公園会議(World Park Congress)でした。この会議の席上で、当時のラヴァルマナナ大統領は、国内の保護区面積を5年で3倍にすると宣言したのです。この発言は「ダーバン・ヴィジョン」として知られています。その後、マダガスカルの5ヶ年計画ともいえる「マダガスカル・アクション・プラン(MAP)2007-2012」において、具体的な数値目標が明示されました。それによると、2007年現在は1万7000平方キロメートルある現行の保護区を、5年後の2012年には6万平方キロメートルにまで増やすというのです。 計算すればわかるとおり、6万平方キロメートルといえば、国土の1割以上にあたります。日本よりはるかに人口が少ないので、国土の1割くらいはたいしたことがないともいえますが、マダガスカルの人口増加率は年間3パーセント近くに達します。このペースで増えていけば、現在2000万人近い人口は、15年後に3000万人を超えます。現在ですら薪や炭などの燃料が少なくて困っている地域が多いのに、15年後にはどうなるのでしょうか? そして、その15年後は? このように考えると、国土の1割を国立公園などの保護区にするというのは、かなり大胆な決断だったことがわかります。
このように課題の多いダーバン・ヴィジョンですが、はたしてどれほど現実的なのでしょうか。現在のいちばんの問題は、2009年3月に大統領が代わってしまって、ダーバン・ヴィジョンが継承されるかどうかがわからないということです。しかしこの問題は、計画が現実的かどうかには直接関係ないので、ひとまず置いておきましょう。その後の進捗についてはさまざまな観点から評価できると思いますが、わたしの印象では、悪く言えば目茶苦茶な計画でしたが意外に着実な歩みをとげています。 その理由のひとつは、海外の自然保護団体(NGO)が国立公園の調査や準備に多大な協力を提供したことにあります。ある推計によれば、ダーバン・ヴィジョンが出された後の2年間で、マダガスカルの自然保護行政に対して3000万ドルの援助がもたらされたといいます。 なぜ、多額の援助が寄せられたのか。マダガスカルでは、「国立」公園の運営を国家独自でおこなうのでなく、しばしば海外の自然保護団体と協力しておこなっています。国の財政規模は小さいので、自前の運営には限界があるのです。いっぽう海外の団体は、固有種の多いマダガスカルで活動していることをアピールすれば、寄付金を集めやすくなります。そうしたところへ、国立公園が急増するというニュースが入れば、各団体は事業規模を拡大するチャンスとばかり、保護区設定の調査に進んで乗り出すわけです。この見込みは、みごとに当たりました。 ダーバン・ヴィジョンが実現にむけて進んでいることの第2の理由は、マダガスカルの人たちがひじょうに協力的であることです。もちろん、計画がズサンであれば地元の反対も根強いでしょう。しかしわたしの知る事例では、地元の人たちが計画の初期段階から協力していて、むしろ彼らの協力が計画を明確化し実現させていると思えるほどでした。 わたしが調査している地域の例をあげましょう。そこはモザンビーク海峡に面する漁村で、サンゴ礁の美しい海でした。2003年、つまりダーバン会議と同じ年、この村にイギリスの自然保護団体が定着し、サンゴ礁の調査を始めました。サンゴ礁水域を保護区に指定するのが目的でしたが、そこでは、たくさんの人たちがサンゴ礁で漁をして暮らしを成り立たせています。ふつうに考えれば、ここに保護区を設定しても、漁師の権利を侵害するだけです。しかし、保護区を設定する前になんらかの保護活動をスタートさせれば、保護区運営の見込みがつき、保護区実現も夢ではありません。
自然保護団体は一計を案じました。漁師の収入源のひとつとなっているタコを、まず保護することにしたのです。稀少なサンゴでもめずらしい魚でもなく、日本のマダコに似たタコです。雨季の7ヶ月のあいだ、のちには4ヶ月半のあいだ、特定の水域のタコの漁を漁師たちに禁じました。すると、解禁直後に大型のタコが多く漁獲され、禁漁に経済的効果があると漁師たちが考えるようになったのです。 その後、タコの禁漁は毎年おこなわれるようになりました。しかし、自然保護団体にとってもっとも大きな成果は、環境保護に関する大きな賞(国連シード賞)を獲得したことです。その表彰理由は、周辺住民が保護区の運営に積極的に参加するあたらしいタイプの自然保護を実現したことにあります。 住民側もにわかに活気づきました。複数の村からプロジェクトに関わる代表が選出され、一種の組合組織ができあがりました。この積極性が評価され、組合は国連赤道賞とWWFのゲッティー賞を受賞するにいたっています。
この地域にも、自然保護団体の活動に否定的な人たちがいるかもしれません。しかし、それにもかかわらず、地元の人たちの協力により団体の活動が推進されてきたことは否めません。当初、保護区の設定自体が危ぶまれていた地域が、地元の人たちの協力によって保護区化する可能性がでてきました。それどころか、地元の人たちの協力そのものがあたらしい活動として評価され、保護区設定の根拠になりそうな勢いです。あたらしい試みに対する人びとの理解が、マダガスカルの環境保護にとっては希望の光となったのです。 (いいだ たく) |



