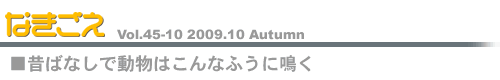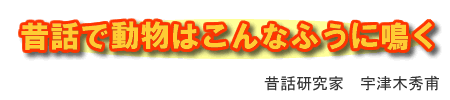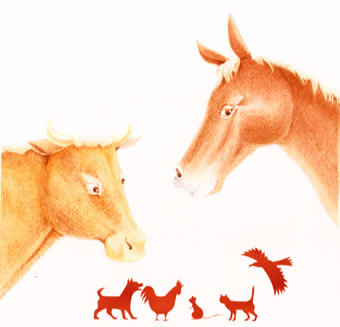|
古代では、動物の鳴き声も風雨の音などとともに、自然神の声として聞いたと思います。その神の声を擬声語で発声しながら、その動物や波の動きなどを真似ながら繰り返す動作(舞踊化)をすることによって自然神を克服できると意識していたようです。古代人はそうすることで自然を超え、自由(人間が万物の霊長である証拠)を獲得したのです。
ところがこの人間の自由が、階級差別が発生しますと、奴隷視された人たちが、悲しいことですが、人間の尊厳性を喪失するようになってしまったのです。平安時代から鎌倉時代にかけての身分制度で下層とされた人々は自然神、例えばヘビなどを極端におそれるようになりました。
室町、戦国、そして江戸時代になりますと、最下層とされていた商人が経済発展とともに浮上し、農民とともに自由を取り返すようになり、昔話が生み出されることになりました。昔話では人々は動物を身近にひき寄せ、鳴き声に親しむようになりました。
江戸時代の中期にはペット趣昧がはじまり、イヌやネコを下層町民までが飼うようになり、「猫ことば」が流行しました。せまいひたいを「猫ひたい」、熱いものが食べられないと「猫舌」、「猫なで声」などの言葉まで生まれました。
○昔話『動物のお伊勢まいり』
(大阪の代表的な動物ばなしで、まずネコが登場します)
自尊心があるネコがさびしくなってネズミをつかまえた瞬間に「おまえ、わしの友達にならへんか」と聞いてしまいます。食べられると思っていたネズミは大よろこび。「友達になります」と答えます。
(動物も普通の人間のようにしゃべらないと話がすすみません)
ネコにネズミの友達ができて、カネもないし、歩いてお伊勢まいりに行こうと決めると、ネズミが云いました。「ひとがみたら、ネコとネズミが友達やなんて、笑いよりまっせ」、どうせおかしな友達なら、ネズミが卵を盗みにいくニワトリ小屋に行ってニワトリさんに声をかけてみますと云って、ニワトリも友達にしてしまいます。ニワトリはイヌに声をかけて、イヌも友達になって伊勢まいりに行くことになりました。途中でウシとウマと、空を飛ぶ夕力も仲開になるのです。「カネがないもんどうしが、歩いてお伊勢さんに参るんじゃ」と元気一杯です。
さて、いっしょにお伊勢さんを拝んで、次に二見(ふたみ)の浦の見物に行くのですが‥‥.
|
ネコ 「これ ニャーンぼ」
ネズミ「チュー文(十文)」
夕力 「ターカィな」
|
沿道にみやげもの店が並んで、「いらっしゃい、いらっしゃい。笛どうです、よお嗚リまっっせ」、「しょうが板どうですか」、「きれえな色がついた貝がら、買うてちょうだい」と声をかけてきます。
「あかん。のぞいたらあかん。わしらはカネないねんさかい」と、みんなが下をむいて歩いていると、貝殻があんまり綺麗に見えたので、ネコが店にとびこんでしまいました。「これ、ニャーンぼ?」そしたら、ワアッとみんな店にはいってしまいました。瞬間に、みんなが、「ああ、店の人が値を云うたら買わんならん。出んとあかん」と思うのです。と、ネズミが「チュー文、チュー文」(10文。昔の金額)店の人より先に値を云うと、夕力が「ターカィな」と叫んで、それでみんながドッと店から出ることが出来ました。
(なんとも器用に鳴きますね)
みんながゾロゾロ、二見の浦にくると、二つの岩があってその開に縄がはってある。「ほう。あの間からお日イさんがのぽるのやて。見とかんとあかん」とみんながしゃがみこむと、人が「あんたら、なにしてんの」と尋ねました。「二つの岩の開からお日さんが上るのん、待ってる」と答えます。すると「アホやなあ。お日さんがのぽるのんは朝やで。そこらの宿にとまって、朝に見においで」と云われてしまいます。「宿屋なんて、カネもないのに泊めてくれへんで。どないしよう」とへたりこみました。ウマが「ヒヒーン、日が暮れたァ」と鳴き、ウシが「モーいの」と鳴きます。イヌが「イヌ道、忘れた」と鳴きます。
(ここまでくると無茶苦茶な鳴き方をしてしまいますが、話を聞く者は疑問を感じずに、鳴き声として聞くのです。昔ばなしは妙なもので、イヌの鳴き声などヒドイものですね)
ニワトリだけは悠々と「コッコッ。コッコッ」と土にクチバシを突っ込んで、なにやら食べはじめました。「ニワトリさんはええなあ」と眺めていると、ニワトリが鳴きました。
「コッコッ、コッカラコーイノ」みんながそれを聞いて、その道を歩くと、大阪に帰ってこれました。
おしまい。
(目で読むとヘンテコでも、聞いているとヘンテコな鳴き声でなくなるから、面白いのです)
◎『ゴンベさんとニワトリ』の話
昔、ゴンベさんが川のそばで鍬うちをしてると、堤防の松の木でカラスが「クワー、クワー」と鳴きよる。「ああ、日が暮れるな。もういなんとあかんな」、ゴンベさん、川で手を洗おて帰りかけると、カラスがまた「クワー、クワー」と鳴きよった。
ゴンベさんは家へもどって「ただいま」と声をかけると、嫁さんが迎えに出てきて「あんた!手ぶらですか?鍬を田んぼに忘れてきやはりましたな」と云うた。そこでゴンベさんは「ハッ」と気がついたと云うんです。
「昔から、ゴンベが種まきゃカラスがほじくる、云うて、たいがい迷惑をかけられてる。けど、あんな畜生でもチャンと恩義を感じてるとみえて、わしがもどるときにクワー、クワーと鳴いて教えてくれとった」ゴンベさん、そう感心したと云うんです。その時、軒先のニワトリをみて、怒ったんです。
「やい、カラスでもな、恩義を感じてクワー、クワー云うて、鳴いて教えてくれよるど。それにおのれはなんじゃい。ちゃんと人様の軒先に住まわしてもろおて、朝、昼、晩、三度三度のゴゼンもちゃんとよばれてる。それに、いっこう、卵も産みくさらん。そんなど畜生は出ていけ」
そしたらニワトリが、声を振りしぽって、鳴きよりました。
「トッテコーカー!」
田んぼに忘れた鍬を、とってこうか、と鳴きよりました。これにはゴンベさん、また感心してしもうて、それから百姓は、ニワトリが卵を産んでも、産まんでも、だいじに飼おておるのやと云われてます」
(動物だちと日常的に対話をしていた百姓の様子がよくわかるでしょう。動物の鳴き声を天からの声のように聞くこともあって、それを頭の中で反芻していると、親しさが一層深まった鳴き声もあったのです)
以上
(うつき しゅうほ) |