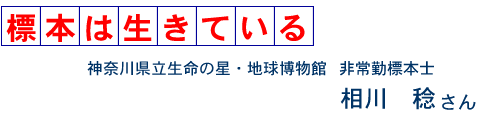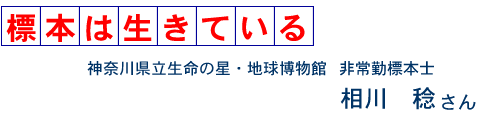僕が毎日付き合っている動物たちはもう生きていません。死んでいます。
そんな死んだ動物たちを僕は博物館で標本として残せるようにする仕事をしています。剥製や骨格標本をつくる人、といえばピンとくる人もいるかと思います。「剥製」というと何だか不自然な姿勢で、気の毒そうな顔をしてホコリをかぶって、なんか気味悪い…そんなマイナスのイメージを持っている人も多いと思います。残念ながらそういう印象を与えてしまう標本が多いのは事実です。でも、生きた動物がそうであるように、標本になった動物も、少なくとも生きていた時と同じくらいに不思議さや発見・感動を与えてくれるものだ、と僕は思っています。
実際に標本をつくってみると、知っているつもりでいた動物のことを実は何も知らなかった、ということがよくあります。鼻の形は?瞳の色は?耳の位置は?まぶたはどんなだった?わきの下にシワはできる?指の角度は?この骨こんな形だったっけ?…。そう四苦八苦しながら標本をつくっているとその動物とさらによく知り合えたような、そんな気がしてきて、時間を忘れてしまいます。
死んだ動物たちは博物館にいます。もちろん「死体」としてではなく「標本」として、です。動物の生きていた証拠を標本として残すことは歴史を記録することでもあります。骨という標本になってからようやく見えてくることもあります。すぐその場でわかることがなくても、20年、50年と標本を蓄積していくと見えてくることもあって、そのために博物館はせっせと標本を集めています。そしてただ集めるだけでなく、動物園などとは違った視点から動物を見ることができるように展示しています。それが僕のような「標本士」の仕事です。
死んでしまった動物たちを生き返らせることは僕にはちょっと無理な相談ですが、せめていい標本として生きられるようにしてあげないと、と思うのです。