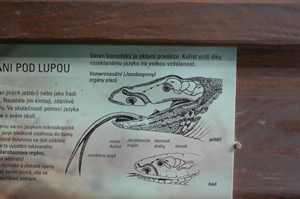昨年の秋、久し振りに龍に会ってきました。 といっても、龍は架空の動物ですから実際に会うことはできません。私が会ってきたのは「コモドの龍」と呼ばれるコモドドラゴン、正式な和名を「コモドオオトカゲ」と呼ぶ動物です。場所はチェコのプラハ動物園です。 世界中の主だった動物園や水族館が加盟する世界動物園水族館協会という組織があります。天王寺動物園も会員なので毎年開催される総会に出席しています。総会は各園で持ち回りで持たれ、昨年の担当がプラハ動物園だったのです。 コモドの龍との出会いは大変幸運でした。園内を歩いていて通りがかった爬虫類館には希少なガラパゴスゾウガメが展示されているということだったので、入って探したのですが見つけられませんでした。そこで、通りかかった飼育担当者らしき人に展示場所を尋ねたのですが、私が総会出席者と気付いたその方は「それよりコモドドラゴンを見たくないですか」とバックヤードへ案内してくれたのです。その人こそ、世界で初めてコモドオオトカゲの繁殖に5回も成功した爬虫類担当課長のピーター・ヴェレンスキーさんでした。世界的に見るとコモドオオトカゲの繁殖に成功した動物園は1992年(平成3年)に初めて成功したアメリカのワシントン国立動物園を筆頭に8園で17回あります。しかし、1園で5回もの繁殖に成功しているのはここプラハ動物園だけです。5回の繁殖で32頭の子供が誕生しました、と大変誇らしげにおっしゃっていましたが、これは十分に自慢することができる記録だと思います。
案内されたバックヤードの第一室に入りました。その部屋には2m程の子供たちが4頭飼われていて、時ならぬ来訪者を好奇心いっぱいの目で見つめ返してきました。中はむせかえる暑さです。この日は10月のプラハとしてはかなり暖かい24℃でしたが、バックヤードはこの時点で30℃でした。むせかえるはずです。しかし、温度はさらに上がり続け、午後2時には40℃にまで上げるのだそうです。この温度の上げ下げがコモドオオトカゲを健康に飼育し、繁殖成功につなげる大きな要因となるそうです。
両親は2004年(平成16年)にインドネシアのボゴールにあるタマンサファリから贈られました。当時2歳4か月だったそうです。その後、順調に成育しましたが、それは彼らが要求する至適温度を提供できたからだそうで、繁殖の成功にもこの至適温度が大変重要な要素となったといいます。というのは野外でコモドオオトカゲの体温を測った結果28~36℃と大きな差があったそうです。自分で体温調整ができない変温動物であるトカゲの仲間にとって体温を保つために外気温からの熱の補給がとても大事になってきます。そこで、気温の低い時には直射日光を浴びて体温をあげ、あがり過ぎると今度は日陰に行って体温がそれ以上あがるのを防いでいるそうです。それを再現できるようにバックヤードでは大きな温度変化をつけられるようにし、それが繁殖の成功につながっているのだそうです。
温度とともに大きく変わったのは給餌の仕方です。繁殖した両親は来園当初はこれまでのやり方通りラットやモルモット、ウズラやニワトリ、ウサギなど様々な種類のエサを与えることが重要と考え、週ごとにエサの種類を変えて与えていました。しかし、このやり方ですと時々食欲を失うことがあったのだそうです。そこで3年目から給餌方法を大きく変えました。野外研究の成果を踏まえて半割りにしたヤギやヒツジを1カ月に1回だけ与えることにしたのです。それも皮や内臓を付けたままで与えるのです。するとコモドオオトカゲたちは必ず腸や肝臓やその他の内臓から食べ始めるのだそうです。それらをすべて食べ終わってから、はじめて肉を食べだすのだそうです。慣れてくると蹄すらも食べてしまうようになったそうです。こうすることで1回の食事で2.5から5kgも食べ、その割には太り過ぎもせず順調に成育しました。この飼育方法は今やヨーロッパ動物園協会のコモドオオトカゲの飼育マニュアルにも記載されているそうです。
その他、卵を産むために地面を80センチも掘る母親のために深い砂場を用意したり、産んだ卵の孵化率を上げるために孵卵器にそれらの卵を移したり、ヴェレンスキーさんの様々な努力や工夫が、この5回の繁殖の成功につながったのです。 東南アジアの孤島に住むコモドの龍たち。狭い島は少しの気候変動や人為的なかく乱で生息環境は急激に変化する危険性があります。そしてその変化が龍たちをたちまち絶滅の淵に追いやることも十分に考えられます。想像上の動物である龍が、コモドの龍として、この地球上にいつまでも生存できるように努めることは現代に生きる私たちの責務だと思います。 (長瀬 健二郎) |