
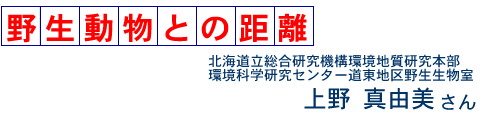
高校時代の私にとって野生動物はテレビで見るものでした。画面には等身大の姿が映り、動物たちの息づかいまで聞こえてきそうな臨場感です。大学時代には野生動物の死因を調べるために動物園に通いましたが、やはり野生動物は自分の目の前に横たわっていました。しかし、今、北海道で野生動物の保全と管理に関わる仕事をしていますが、彼らを間近で見る機会はほとんどありません。私が研究しているニホンジカは日の出や日暮れに活発に行動するといわれていますが、夜にならないと出てこないことも多いのです。また、たとえ姿が見えても、100m以上も離れているので双眼鏡が欠かせません。しかも、彼らは人間を警戒しているので、なかなか自然な行動をとってくれません。実はこれが本来の野生動物の有り様で、TVや動物園こそが恵まれた特殊な環境なのです。ニホンジカの生息数や分布を調べていますが、人間や家畜のようにはっきりした数字を示すことはできません。また、彼らを捕まえて調査しようと思っても、耳も鼻もきく彼らは、おびき寄せに撒いた餌だけしっかり食べて、姿を隠します。野生動物は人間社会の範疇を超えたスケールの中で生きていて、私たちはその生態のほんの一部を理解できているに過ぎないなと感じさせられます。広く長く根気よく調べていくことが野生動物の保護管理には必要です。だからこそ、動物園に行くと、その目の前の迫力に感動します。行けば必ず動物が見られるという安心感もまたうれしいです。さらに動物園には野外では検証できない課題を解く実験施設という可能性も秘めていると思います。餌のメニューから住処の環境まで様々な条件を統制できている動物園は、野外個体群の比較対照にもなるでしょうし、仮説を検証するための実験も設定しやすいです。動物園は従来から希少動物の保全活動に貢献してきましたが、過剰状態にある野生動物の問題解決に果たす役割も同様に大きいと思います。 (うえの まゆみ)
|
