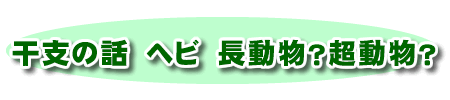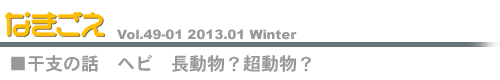
ヘビほど毀誉褒貶(きよほうへん)の激しい動物はいないでしょう。朽ち果てた縄との意味で「朽ち縄(くちなわ)」と呼ばれるように手足のない細長い姿形やにょろにょろと動いたりする様子が気味悪がられたり、あるいは有毒の種がいることから恐れられたりするのでしょう。まさに心底嫌うことを「蛇蝎(だかつ)(ヘビとサソリ)のごとく嫌う」という言い回しもあるくらいです。また一方で、長期間餌(えさ)を食べずに生きていけることや脱皮して皮膚がその都度新しくなることなどから生命力の強い神秘的な力を持つ動物として崇拝されることも多いといわれています。例えばギリシヤ神話に由来する「アスクレピオス(医学の神様)の杖(つえ)」と呼ばれる杖(つえ)に一匹のヘビが巻き付いた図案は世界各地で医療や医学のシンボルとして救急車に描かれたり、また、世界保健機関WHOのマークにも使われています。このようにひどく嫌われたり恐れられるか、はたまた崇拝の対象であったり、ヘビにとっては迷惑なことの方が多いのかもしれませんが、一方ではわれわれ人間にとっては強い存在感があります。また、視点を変えれば近年はヘビをペットとして飼う人もいることから、別の意味でヘビに好意的な人も出てきているようです。 ヘビの祖先は1億5千万~1億年前(中生代白亜紀)に出現したといわれています。ヘビは分類学的には爬虫綱(はちゅうこう)、有鱗目(ゆうりんもく)、ヘビ亜目に属する動物の総称で、同じ有鱗目(ゆうりんもく)のトカゲの仲間から進化したと思われます。そして、ある種のトカゲが地中生活に適応した結果、手足のない現在のような形を得たと考えられています。現存のヘビは3,000種以上おり、南極やニュージーランドなどを除く大陸や周辺の島の砂漠、草原、森林、海洋など様々な環境に適応して暮らしています。そして現存の爬虫類(はちゅうるい)としては最も栄えているグループであるといわれています。ヘビは手足がなく細長いといった姿ですから、解剖学的にもその体型に見合った特徴を持っています。その骨格は頭の骨とたくさんの背骨とこれにくっついている肋骨(ろっこつ)からなります。また、左右の下あごの骨はくっついておらず、そのため口よりも大きな獲物をのみ込むことができます。肺や肝臓などの内臓も、うまい具合にあの細長い体の中におさまっています。肺は右側が大きく、左が小さいか、あるいは退化してなくなっています。そして発達している肺も細長く体長の2/3近くもあります。肝臓はやはり細長く、肝臓で作られる胆汁は少し離れた場所にある胆嚢(たんのう)に蓄えられます。腎臓(じんぞう)も細長く、右側の腎臓(じんぞう)の方がやや前にあります。こうした内臓を細長い体に収容しながら、しなやかに体をくねらせて非常に巧みに移動します。様々な環境に生息し、手足がなくても地面をはい進んだり、水上や水中も、また、樹木に登ったりと、およそ自分の生息環境の中であれば自由自在に行動することできます。 天王寺動物園のは虫類生態館(アイファー)で飼育しているボアコンストリクターというヘビは暑くなると飼育室のプールの中や地面にいることが多いのですが、寒くなると飼育室を暖めるための電灯に近い棚の上に、この能力を活用して上っています。この場所に上るには、でこぼこの少ない擬木(作り物の木)に尾を巻きつけて上半身を棚に向けて伸ばし、頭部を棚の上にのせて手近なものに固定し、他の部分を収縮させて棚の上に徐々に上るという方法をとっています。本来この棚は、飼育室の観覧用のガラス窓の上にあって、ヘビが高い位置に上らないように取り付けたバリアーだったのですが、ヘビの運動能力が人間の浅知恵を上回っていたのです。そのため、現在では電灯や棚の周囲も網で覆って中に入れないようしてあります。 ヘビは手足がないという以外にも瞼(まぶた)と外耳がないという特徴があります。全身が鱗(うろこ)に覆われており、目の部分のみが透明で目の所在はわかりますが、耳の所在はわかりません。ヘビ類は全て肉食で、それぞれ獲物となる動物を狩るために視覚や聴覚、嗅覚(きゅうかく)がそれに合わせて発達しています。例えば、ヘビが先の二つに分かれた舌を出してプルプルと波打たせ、そして、引っ込めるようなことをしているのは空気中の匂いの粒子を口の内側上部にある匂(にお)い感じるセンサー(ヤコブソン器官)に送っているのです。この匂(にお)いセンサーは獲物を追跡したりする場合にも、繁殖期には相手を探したり、捕食者から逃れたりすることにも非常に役に立っています。さらには熱センサーまで持つものもいます。それはピット器官と呼ばれ左右の目の下にある窪(くぼ)みで、動物などの出す赤外線を感じることができるのです。 このようにヘビの特徴をみてきますと、いろいろな環境に適応進化してきた結果、さまざまな能力を獲得してきたゆえの長動物、超動物であるといえると思います。この稿に添えた写真は天王寺動物園のは虫類生態館のボアコンストリクターです。15分くらい見ていると例の棚にはい上がり、結局、網で覆ってあるため棚に入ることができず、元の場所に戻りました。爬虫類(はちゅうるい)は活発な動きを見せることは少ないかもしれませんが、ゆっくり見ていると思わぬ動きに遭遇することがあります。時間に余裕がおありでしたらヘビ年でもあり是非爬虫類(はちゅうるい)生態館アイファーまでお越しください。
(天王寺動物園長 高橋 雅之)
|