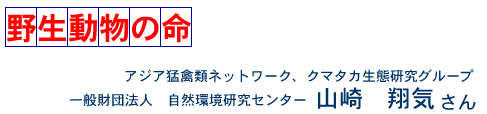私は命を平等に尊重した上で、状況に応じて「命を救う選択」と「命を奪う選択」をしています。この命に対する一見矛盾した真逆の行為には、私なりに矛盾していないと考える理由があります。
私は幼少のころから父親に連れられて、生態系の頂点に位置するイヌワシやクマタカなどの猛禽類を観察してきました。そして、次第に猛禽類を保全したいと思うようになり、大学進学を機に猛禽類のみならず生態系に関わる様々な生き物について知ろうと思いました。
進学後、動物園には普段ゆっくりと見られない動物を観察するだけなく、動物たちを取り巻く現状や保全活動について学びに行きました。また、野外には種を問わず各地へ足を運び、幅広い視点に基づいた生態系について勉強してきました。その結果、私が関心を抱いてきた猛禽類の生息地には、希少種保護活動のみならず傷病鳥獣救護、サルやシカなどによる農林業被害への対策、狩猟など様々な考え方と取り組みが混在することに気づきました。そして、これらを知れば知るほど生態系保全について深く考え、その一語に詰まる意味の大きさを実感するようになりました。
現在、私は主に希少猛禽類とシカなどの増えすぎた種を対象とした調査・研究の仕事をしています。絶滅が心配される希少種は、生物多様性保全のために保護をする必要があります。一方で、自然植生を破壊するほどに増えすぎた動物は生息地保全のために数を減らす必要があります。私が行っている一見矛盾した「命を救い・命を奪う」という選択は、どちらも生態系保全への貢献が最終目標です。複雑な関係で成り立つ生態系を、どのように保全すればいいかという明確な方向性を見出すことは困難です。しかし、それを少しでも明確にするためには地道にデータを蓄積し、横断的に幅広い視点から考えていくことが重要だと考えています。命の選択という重い決断には、個体の背景を含めた勉強をし続けることが欠かせません。