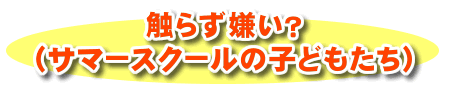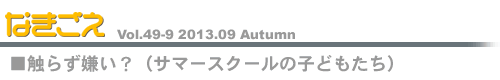
飼育係になって10年目になる私の苦手な生き物は、カブトムシの幼虫、ナメクジ、ミミズなどでした。手触りがムニュッとヌルッとしている、そういうイメージだったからです。最近の子どもたちがマイナスのイメージをもつ生き物はけっこう多いのではないでしょうか。私が今担当している爬虫類はその代表格でしょう。 先月、サマースクールを行いました。小学校の高学年の児童を対象に、一日動物の世話をしてもらったり、動物について学んでもらったりする催しです。事前のアンケートに苦手なものがあれば記入してもらうのですが、ダントツで爬虫類が多かったのです。 爬虫類のグループでは、いろいろ体験してもらう中で、ヘビに触れてもらったり、ヘビが餌を食べる様子を観察してもらったりするプログラムを含むことが多くあります。めったにない体験をしてほしいという思いや、ヘビに対するマイナスのイメージが少しでもいい方へ変わってくれたらという思いからです。 ヘビが餌を食べる様子を観察
ヘビを目の前に差し出すと、「キャー」「怖い」「イヤだ」という子どもが多いのですが、こちらがしっかり持ち、間違ってかまれたりしないようにヘビの顔の前に手を出さなければ安全だということを説明し、1回触ってみてと促すと、触った子どもはたいてい「サラサラしてる」「気持ちいい」と言って何度も繰り返し触っていました。ヘビが餌(マウス)を食べる様子は、「かわいそう」と言いつつも、興味深そうに最後までしっかり観察してくれました。 また、コオロギをトカゲやカメに餌としてあげてもらうことも多くあります。このときに驚くのが、虫を触れない子がとても多いことです。たいていの小学生が昆虫少年だったのはもうだいぶ昔のことなのでしょうか。「気持ち悪い」「かまれる?」と尻込みする子たちを励ましがんばってもらうと、次第にコツをつかみ上手につかまえられるようになります。 一日、爬虫類に接していると、午後のサマースクール終了時間には、それまでばく然といだいていたマイナスイメージが少なくなっている子が多いのです。最初カメやヘビを怖がっていた子たちに、「ちょっとはヘビとか好きになった?」と聞いた時、「うん、好きになった!」と答えてもらえると、そのことに貢献できたことが嬉しくなります。 なんとなくわからないまま、苦手なイメージをもってしまうことのないよう、子どもたちが動物や昆虫に触れる機会が増えたらいいな、と思っています。
カメ、ヘビ、ワニの観察
現在、自宅に私の苦手だったカブトムシの幼虫が40匹ほどいます。昆虫好きの息子と一緒に飼い始め、触ってみると、小さい時こそムニュッとしていますが、大きくなった幼虫は筋肉質な手触りでした。また、去年動物園で飼育していたモグラが与えていた餌を突然食べなくなり、死なせるわけにはいかないと園内でミミズをさがすことになりました。植え込みの下を掘り、数十匹のミミズを集めたのですが、少しひんやりしていてイヤな感触ではありませんでした。ナメクジだけは、まだ手の上に乗せてみる勇気が出ないのですが…。 (中島 野恵)
|