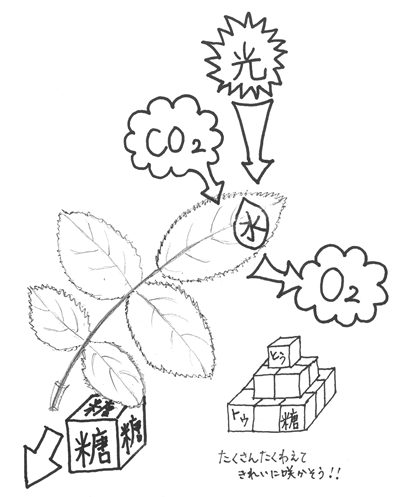多くの人に愛されてきた花、バラ。美しい形や甘い香り、するどいとげが特徴です。ポピュラーな花ですが、草花ではなく、木に咲くことを知っている人は少ないと思います。世界中に何万という品種があり、その多くは、冬になるとモミジやイチョウのように葉を落とす落葉低木です。春にしか咲かないものもあれば、年中花をつける四季咲きのものもあります。 四季咲きといっても、見応えのある花を咲かせるのは春と秋、5月と10月です。前の年に蓄えた養分を使って一斉に咲き誇る春の花は大変豪華ですが、その一方、数は少なくとも一輪一輪が美しいのは秋の花です。なぜ秋はきれいに咲くのでしょうか? 9月半ばを過ぎると、気温はどんどん下がります。大阪の平均気温でいうと、10月1日の最高気温は約26℃、最低気温は約18℃ですが、月末には最高が約20℃、最低が約12℃へと下がっていきます。バラが育ちやすい温度は20℃前後から25℃ですから、日中は活発に光合成をおこなって成長します。一方夜になると、低温のために活動がゆるやかになり、日中に光合成で作り出した糖をためこみます。この糖が、花を咲かせるために多く使われるために、色がより深くあざやかになり、香りも強く形も良くなります。しかもすぐには散らず、長持ちします。 さらに気温が下がると生育はゆるやかになって、最高気温が7℃を下回る12月末ごろから2月末までは活動を休止します。春から秋の間に伸びた緑色の枝は、寒さにあたると赤く変色します。これは、バラが寒さから身を守るために、糖からアントシアニンという色素を作り出すからです。目の健康にいい色素と言われ、ブルーベリーに多く含まれていることで有名なアントシアニンですが、糖の濃度が高くなければできない物質なので、赤くなった枝には糖がたくさん含まれているといえます。アントシアニンには、寒さや紫外線などの外的刺激から植物を守る働きがあります。葉っぱで光合成して作り出した糖が、冬には枝を守るために使われているのですね。さらに余った糖は、春になったら芽を吹くための大切なエネルギー源として、根で蓄えられています。 バラ以外の植物でも、冬の寒さから体を守るために糖が使われています。身近なところでは、お鍋料理などにするとおいしい冬野菜がそうです。白菜や大根が凍ると細胞内に含まれている水が膨張し、細胞壁を壊してしまいますが、これをふせぐために糖が使われています。水に砂糖を加えると、凍る温度が低くなる現象が起きます。「凝固点降下」といい、一定の濃度までなら高くなるほど水が凍りにくくなる現象を利用して、冬野菜は氷点下の寒さに負けないための工夫をしているのです。野菜たちの努力は私たちの食卓をより豊かなものにしてくれます。霜が降りたら、白菜の芯に近い葉を生でかじってみてください。さわやかな甘さが感じられる、冬の恵みです。 話をバラに戻します。枝が赤くなるころにはほとんどの葉をふるい落とし、休眠に入ります。12月下旬から2月初旬のもっとも気温の低い休眠期が注1剪定(せんてい)や植え替え、注2施肥(肥料を与えること)に適していますから、寒くても公園では作業をします。厚い皮の手袋をはめていても、するどいとげに刺されることしばしばですが、冬にしかできない作業をしっかりとおこなわないときれいに咲いてはくれませんので、そこは頑張りどころです。つるバラは枝をアーチやポールに誘引します。剪定と施肥を済ませ、春を迎える準備が整ったバラ園は、ずいぶんすっきりした印象になります。お花屋さんではみることのできない秋から冬のバラの姿を、皆さんも公園に見にいらしてください。
(武市 菜穂子) (注1) 剪定(せんてい):枝を切ること (注2) 施肥:肥料を与えること
|