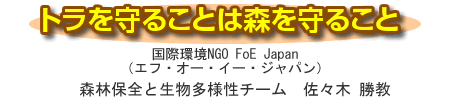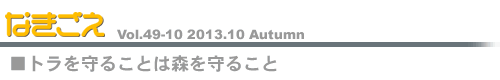
アムールトラ
100年前には10万頭いた野生のトラも、今では5000~7500頭だと聞いたのは、既に10年以上も前のこと。広大な縄張りを必要とする野生のトラたちは、20世紀の100年間に生息地の93%を奪われ、絶滅危惧種としてレッドリストに登録されるまでになりました。遠い存在と思っていた野生のトラが、実は日本から程近い極東ロシアにも生息していることを知ったのは、前職であるロシア語翻訳に従事していた時。それがネコ科最大と言われるアムールトラとの出会いでした。現在の職場であるFoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)で働き始めたのは、この極東ロシアで森林生態系保全活動を行なっている環境団体だったことが理由でした。近くて遠い存在である野生のアムールトラと私たち日本人のつながりは何か?そしてその森を守るためにできることは何か?を模索する10年が始まりました。
ウスリータイガ
広大なユーラシア大陸の南東に位置する極東ロシアのなかでも、アムールトラの生息地と言われている地域は、日本海に面した沿海地方とハバロフスク地方の一部のみ。生息に適合すると判断されたのは面積にして352,740km2と、ほぼ日本列島に相当する広さであり、そこに野生のアムールトラの95%が生息していると言われています(Miquelle et al (2007))。この地域の森林はロシアの他の地域とは異なり針葉樹と広葉樹の混交する温帯林であり、アムール川の支流であるウスリー川にちなんでウスリータイガと呼ばれています。これがアムールトラの別名であるウスリートラの由来にもなっています。この森には、エゾマツ、カラマツ、トドマツのような北方林特有の針葉樹の他、ナラ、タモ、ニレのような広葉樹が豊富に植生しており、なかでもチョウセンゴヨウはこの森を特徴づける樹種であり、10cmをゆうに超える大きなマツの球果は、トラが捕食する野生動物のエサとして非常に重要な意味を持っています。
チョウセンゴヨウの球果
ウスリータイガに生息する野生生物は、このようなチョウセンゴヨウを中心とした森林生態系のなかに生きています。チョウセンゴヨウは樹冠が広いため、森のなかには落葉した針葉が幾重にも降り積もり、絨毯(じゅうたん)のような柔らかさを保ちながら、雑草が生い茂るのを抑えています。広々とした森林床の上には、マツの実やモンゴリナラのドングリがぎっしりと散らばっており、これをエサとするシマリス、ウスリーイノシシ、ツキノワグマの他にもアカシカ、ノロジカ、ジャコウジカのような有蹄類(ゆうているい)、ヒグマやシマフクロウなど北海道にも生息する動物たちもいます。このような豊かな生態系の食物連鎖の頂点に位置するのがアムールトラなのです。 野生のトラの生息頭数は2011年に下方修正され、3200頭を残すのみとなりました。アムールトラ(Panthera tigris altaica)は、現存するトラ9亜種のうち最も北、冬の気温がマイナス30℃を優に超える極寒の地に生息しています。シベリアトラ、ウスリートラなどとも呼ばれ、世界遺産である中央シホテ・アリニ山脈を含むアムール川流域の広大かつ豊かな森林地帯のシンボルとみなされています。2004~2005年にかけての冬季に実施された全生息域調査では、428~502頭が生息しているという結果が出されました。前回よりも微増傾向にあるということで、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、絶滅寸前(CR)から絶滅危惧(EN)へと上方修正されていますが、種としての多様性を考えた場合、予断を許さない状況であることは今も変わりません。 では、いったい何がアムールトラの生息を脅かしてきたのでしょうか?ここでは、その要因を開発と密猟の二つに絞って考えたいと思います。ロシア人による極東ロシアへの入植が本格化したのは19世紀の中頃、今からわずか150年ほど前のことです。開発は、大規模に森林を切り開き、大量の木材生産を伴うものでした。アムールトラはこの過程で害獣として排除され、また時には毛皮目的に狩られて行きました。このように開発と密猟は常にセットのようになってアムールトラの生存を脅かしてきました。森林開発が生息地面積を縮小させ、石油・ガスパイプライン建設が生息地を分断してきました。道路インフラの敷設によってアクセスが可能となった森林には、高級樹種を狙った違法伐採者、イノシシやシカの肉、アムールトラの毛皮や骨を狙う密猟者が入り込みます。アムールトラ自体が狙われない場合でも、トラは自らの糧であるイノシシなどの動物を失い、そのイノシシを育てる実をつける木々を失い、縄張りを失ってきました。この開発によってもたらされた木材、石油、ガスを使い続けたのは誰でしょうか?それは他ならぬ私たち日本人なのです。
タイガから輸出される木材
極東ロシアからの木材輸入の歴史は古く、関東大震災の復興資材としても利用されたと言われています。1950年代の木材貿易の自由化を受けて輸入量は劇的に増加し、近年では木材加工地が中国へと移ってはいますが、今でも日本の建築や家具の市場を支え続けています。一方、石油やガス等の天然資源は、日露間の経済協力の中心に位置づけられるほど重要なものとなっています。このように私たち日本人は、知らず知らずのうちに野生アムールトラ生息地の森の恵みを使い続けているのです。アムールトラ自体の密猟防止と同じくらい、その生息地を守ることが重要です。まさに、「トラを守ることは森を守ること」なのです。私たちを含む環境保護団体は、生息地を守るためにあらゆる活動をしています。違法伐採の摘発、貴重な木材の流通調査、敷設されるパイプラインの環境影響調査など。そのなかでも私たちが注力してきたのが、消費者の皆さまに対するこれらの問題の周知でした。しかしながら、木材や石油からアムールトラ生息地を連想するのは簡単なことではありません。けれども、実際に動物園にてアムールトラを見た方々は違います。目の前に存在するトラの息づかいと、生息地で今この時も起こり続けていることを結びつけることができます。野生のアムールトラの未来の一端は、私たち日本人が何を知り、何を選んで使って行くかにかかっているのです。
(ささき かつのり)
|