
野間馬の変遷野間馬など日本在来馬のルーツは、今のところ解明はされていませんが、今から約2000年前アジア大陸から日本列島に伝わってきたといわれています。それ以来、約350年前(1635年)に松山藩主(愛媛県松山市)が今治城主に命じて、来島海峡に浮かぶ馬島で戦いに使用する馬を放牧して繁殖させたのが始まりとされております。この放牧は飼料の不足と病気の発生によって、多くの馬が死んでしまい失敗に終わりました。そこで、藩主は松山領内の野間郷(今治市乃万地区)一帯の農家に飼育させ、繁殖をさせることにしました。当時の馬は今より大きくて体高121cmを基準として、基準より大きい馬は藩主が買い上げ、小さな馬は飼育費の代わりに農家に払い下げられました。この基準以下の小さな馬同士の交配からできあがったものが野間馬とされています。日本在来馬8馬種の中で一番小型で粗食に耐え、扱いやすく蹄鉄(ていてつ)もはかずに70kgの重い荷物を載せて運ぶことができます。江戸時代には、今治地方で300頭ほど飼われていて馬産地として大変栄えていたといわれています。明治以降、野間馬のような小型馬は繁殖を禁止されました。昭和になってからは自動車などの輸送手段が発達するとともに、農業機械の発展などにより野間馬の飼育頭数は激減していきました。1961年(昭和36年)には、愛媛県内で動物園に2頭、松山市の長岡悟さんが野間馬を保護するために、県内各地から集めた4頭を含め6頭のみとなり絶滅の危機となりました。1978年(昭和53年)に長岡さんより野間馬のふるさとである今治市で飼育繁殖をおこない保存をしてほしいと、野間馬4頭(雄1頭、雌3頭)が寄贈されました。これと同時に野間馬保存会を関係機関、団体、有志各位が集い地域ぐるみで野間馬を「ふる里の宝」として大切に保存することになりました。この野間馬の飼育はふるさとであった乃万地区の野間集落で16aの傾斜地を整備し、野間馬の放牧場として新開豊さんが保存飼育責任者として保存と繁殖を始めました。翌年から順調に仔馬が産まれましたが雌馬のみで、1983年(昭和58年)に待望の雄馬2頭が生まれました。以後野間馬の繁殖は順調に進み1987年(昭和62年)には24頭となり絶滅危惧から脱し野間馬の保存見通しが見えてきました。1984年(昭和59年)日本馬事協会による「野間馬に関する学術調査」が実施され、翌年に全国で8番目の日本在来馬として認定されました。1988年(昭和63年)には今治市指定文化財(天然記念物)に指定され、1992年(平成4年)に血統管理を推進するために飼養馬全頭(38頭)のDNA鑑定を実施し親子識別をおこない、2002年(平成14年)から血統管理システムの運用を開始しました。2001年(平成13年)日本馬事協会より全国で4番目に種馬登録の対象として決定され登録を開始しました。1989年(平成元年)には飼養頭数28頭となり放牧場も狭く、新たに1.5haを整備し野間馬ハイランドとして開園しました。以後飼養頭数の増加や来園者の増加に伴い拡張整備の要望、次世代をになう子どもたちの自然体験学習施設の必要性へ対応するために1997年(平成9年)に厩舎、放牧場、遊具、いこいの広場など5.6haを有効に整備してリニューアルオープンをおこない、市民に親しまれるファミリーパークとして新たに出発いたしました。
野間馬の変遷野間馬は未改良の馬で性質は穏和で飼い主によくなつき女性や子どもが自由に使役に使うことができます。体型は体高が平均107cmと小さく、身体に比べて頭が大きい。体長は短くずん胴。尻は短く斜尻。蹄(ひづめ)は丈夫で硬く蹄鉄(ていてつ)はいりません。たてがみは多く、毛色は栗毛(くりげ)、鹿毛(かげ)、青毛(あおげ)、芦(あし)毛(げ)と4種類あります。栗毛(くりげ)は栗のような色で全身黄褐色。鹿毛(かげ)は鹿のような色でたてがみや尾などの長い毛と足の下部は黒色です。青毛(あおげ)は全身黒色。芦(あし)毛(げ)は生まれた時は栗毛(くりげ)、鹿毛(かげ)、青毛(あおげ)ですが年齢が進むにつれて白い毛が生えてきて白くなる馬です。ちなみに天王寺動物園で飼育されている福ちゃんは栗毛(くりげ)です。
野間馬の利活用1978年(昭和53年)にふる里の今治市に野間馬が帰り保存を始めていることなどを知らない子供達に、自分達の住んでいるふる里の良さ素晴らしさを認識させる為に、地元の乃万小学校では野間馬に着目をしていくことになりました。野間馬郷土クラブのなかで野間馬放牧場を訪れ野間馬の観察をしていましたが、始めのうちは野間馬も厳しい目つきでにらんだり、頭を出して噛(か)みつく動作をして、馬の体に触れることが出来ませんでした。放牧場を訪れ観察を続けるうちに馬とのコミュ二ケーションが得られ、馬を触れるようになりブラッシングができるようになりました。1985年(昭和60年)には野間馬クラブを新たに結成し、新開さんの指導で馬に乗れるようになり、子供達も進んでクラブ活動に力を入れ野間馬の色々なことを学び、自主的、自発的な行動が見られるようになりました。野間馬との触れ合いを通じて動物愛護、情操教育など児童の健全な育成を図る学習教材としての利活用が始まりです。今では、野間馬ハイランドでの子供達の乗馬体験をはじめ今治市内外の多様なイベントへの出張乗馬、市内小学校へ出向し野間馬との触れ合い、乗馬など野間馬を使った情操教育、野間馬ハイランドで障害者の方と馬との触れ合いを行っております。
2008年(平成20年)には野間馬の飼育頭数が72頭となり野間馬ハイランドでの適正保存育成頭数を上回り、恩賜上野動物園をはじめ富山県、大阪府、高知県など公的な9施設に16頭を貸出し譲渡をおこない野間馬の認識を計りました。 今後の野間馬保存の課題2009年(平成21年)に策定された今治市野間馬保存計画に基づき野間馬の血統分析による繁殖グループの拡充、家畜伝染予防などによる絶滅回避を図る為、副次育成牧場の整備を検討しながら保存への取り組みを一層進めていきます。
(おおざわ かつゆき)
|
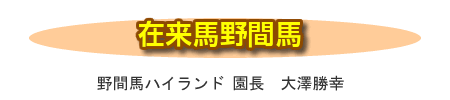
 野間馬ハイランド
野間馬ハイランド 野間馬
野間馬 野間馬クラブ
野間馬クラブ 一般乗馬
一般乗馬 2008年(平成20年)上野動物園へ譲渡
2008年(平成20年)上野動物園へ譲渡