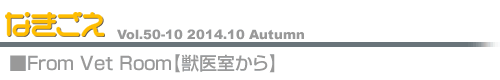
天王寺動物園の園内に、慰霊碑があるのはご存知でしょうか。ペンギン舎の横にひっそりと建っています。毎年9月の秋分の日に慰霊碑の前で動物感謝祭を行い、動物園で、あるいはペットや家畜として人の暮らしの中で亡くなっていった動物たちを追悼しています。慰霊碑の前を通りかかったお客様が「動物のお墓だね」と話されているのを耳にすることがあります。確かにお墓のようなものですが、ここには遺骨や灰などは埋められていません。では、亡くなってしまった動物たちは、その後どうなっているのでしょうか。 動物園で暮らしている動物たちも、いつかは寿命を迎えます。動物が亡くなると、獣医師が解剖して原因を調べます。感染症であったことがわかれば残された動物に拡がらないように予防し、栄養的な問題があったと考えられれば餌の内容を検討しなおすなど、その後の動物の健康管理に活かすためです。 解剖によって、危険な病原体などがないことが確認されれば、多くの動物は博物館に引き渡され、そこではく製標本や骨格標本として生まれ変わります。標本として展示されるものもあれば、収蔵庫で保管されるものもありますが、末永く教育普及や調査研究のために活躍してもらうことになります。はく製標本や骨格標本を作製するには、それなりの技術と労力、時間が必要です。ほとんどの動物が引き渡される大阪市立自然史博物館では、標本作りのボランティアサークルを擁しています。なにわホネホネ団と名付けられたこのサークルは、動物園の動物だけでなく、野外で見つかった動物の死体からも標本作りを進めています。亡くなってしまった動物に、第二の活躍の場を与えてくれる頼もしい存在です。
精子や卵子を残すことができれば、亡くなってしまった動物から子供を得られる可能性が出てきます。不自然な繁殖に思えるかもしれませんが、希少な動物で多くの血統を残していくためには有効な方法です。当園では、神戸大学や近畿大学との連携により、−196℃の液体窒素の中で多数の精子を保存しています。
動物園では、希少種を含む様々な動物を飼育しています。これらの動物は、生きている間はもちろんのこと、亡くなってしまった後でも、私たちに様々なことを教えてくれます。かけがえのない貴重なものとして、大切に扱わなければならないと考えています。
(高見 一利)
|
||||||


